制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を中学生から高校生年代まで延長
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
※18歳~22歳の児童は、保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費(生活費や学費等)を負担している場合に限り第3子以降の算定対象として数えられます。
(5)支払月を年3回から年6回に増加
制度内容の比較
| |
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
| 支給対象 |
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
| 手当月額 |
0~2歳 |
15.000円 |
0~2歳 |
15,000円 |
第3子以降
30,000円 |
| 3歳~小学生 |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 |
| 中学生 |
10,000円 |
中学生 |
10,000円 |
| 高校生 |
支給なし |
高校生 |
10,000円 |
所得制限あり
所得制限限度額以上の場合→ 児童1人あたり5,000円
所得上限限度額以上の場合→ 支給対象外 |
所得制限なし |
| 第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
| 支給月 |
2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給 |
新たに受給者となる方
以下の(1)~(2)に該当する方については、今回の制度改正により、新たに申請が必要となります。8月下旬頃に申請書等を郵送予定ですので、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にて申請をお願いいたします。
公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。
(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
(2)制度改正前の所得制限を超過し、児童手当の受給資格がない方
手当額が増額となる方
以下の(1)~(3)に該当する方は、今回の制度改正により、手当額が増額となります。(1)~(2)に該当する方は申請不要ですので、10月以降に発送予定の通知にて金額をご確認ください。
(3)に該当する方は監護相当・生計費の負担が分かる書類等の提出が必要となりますので、こども未来課窓口または郵送にて申請をお願いいたします。
公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。
(1)受給資格がある方で高校生年代の児童を養育している方
(2)制度改正前に特例給付となっている方
(3)18歳年度末以降22歳年度末までの児童と、高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方
※18歳~22歳の児童は、保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費(生活費や学費等)を負担している場合に限り第3子以降の算定対象として数えられます。
児童手当制度改正 手続き要否フローチャート
制度改正による申請(認定請求)の要否は下記フローチャートをご確認ください。
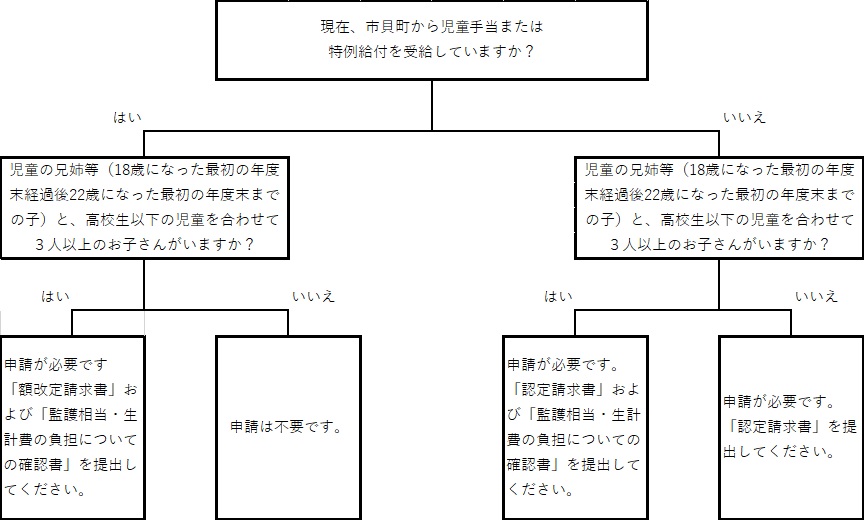
申請に必要な書類(様式はページ下部に掲載しております)
・児童手当 認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(確認書は18歳年度末以降22歳年度末までの児童と、高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方のみ提出いただく必要がございます)
申請に必要なもの
【全員共通で必要なもの】
・印鑑(認印可)※受給資格者本人が申請をする場合は省略できます。
・受給資格者名義の普通預金通帳 ※児童や配偶者の口座は指定できませんのでご注意ください。
・受給資格者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
(通知カードの場合は、運転免許証・パスポート等の写真の表示がある身分証明が必要です。)
【状況により必要なもの】
○社会保険に加入している場合:健康保険証
○請求者が児童と別居している場合:別居児童のマイナンバーがわかるもの
※窓口にて「別居監護申立書」をご記入いただきます。
※別居監護の認定は、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により一時的に児童と別居(国内)しているなどの条件を満たす
必要があります。
※児童が海外留学している場合は、別途条件があります。
※未成年後見人、父母指定者等、父又は母以外の方が請求する場合は、別途必要となる書類があります。
申請場所
○市貝町に住所がある受給資格者の方
市貝町役場 こども未来課
○他の市区町村に住所がある受給資格者の方
住所がある市区町村の児童手当担当課
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
届出内容に変更があった場合
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
・養育している児童の数に増減があったとき
・受給資格者が公務員になったとき
・児童と別居するとき
・振込口座を変更するとき(児童や配偶者など、受給資格者名義の口座以外は指定できません。)
・結婚・離婚・死亡等により、受給資格者が変更になるとき
・市貝町から転出するとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要です。)
・受給者が死亡した場合
児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に
代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。また、亡くなられた方にまだ支払われていな
い手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。